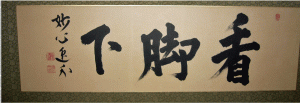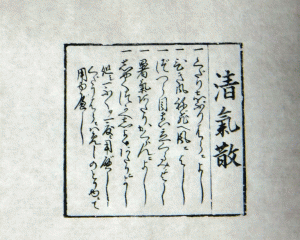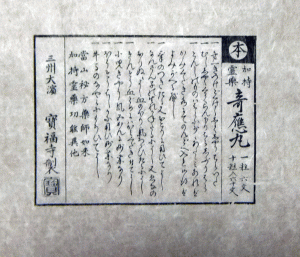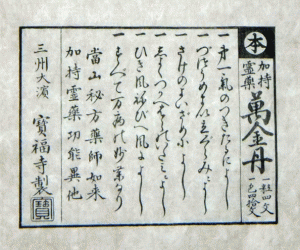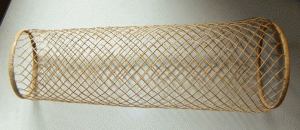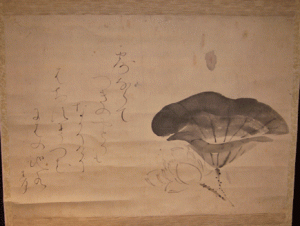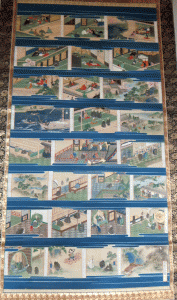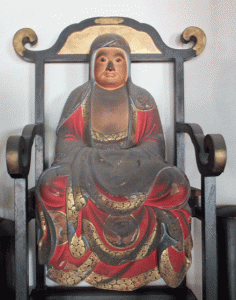住職の独断と偏見で綴ります。
お寺のよもやま
商品
梶浦逸外
清気散
焼香
仏教行事では焼香する事が多くありますが、皆さんは焼香をどのようにしてみえますでしょうか?
意味合いは、お亡くなりになられた方などに、香りをお供えをするという事です。
作法は実は宗派によって様々であります。曹洞宗では、まず御霊前などに向かい合掌礼拝をし、ひとつかみのお香を右手の親指・人差し指・中指の3本の指で自分の額の辺りまでつまみ上げ、お亡くなりになられた方の事を思います。その時に左の手を添えます。そして炭にくべます。再度、右手で同じようにお香をつまみ、2度目は左手は片手で合掌し、上に持ち上げずに、そのまま炭にくべます。2度目の焼香の事を従香(じゅうこう)と呼びますが、お葬式などの時には1度目の焼香で構いません。2度目は添えるという意味合いです。茶道の世界でもお抹茶茶碗を回しますが、やはり1度で回すのではなくて、2度目を添えます。日本人の奥ゆかしさを表現しているのです。
また、他の宗派では、3回の焼香をするところもありますが、心を込めてお供えをして頂けたなら、きっとお亡くなりになられた方に気持ちが通じていく事と思います。
版木3 奇應丸
「ヒヤ、ヒヤ、ヒヤの、ひや・きおーがん」のコマーシャルソングを思い出します。樋屋奇応丸。この奇應丸が、寳福寺でも売られていたとは江戸時代でもかなり人気のお薬であったんでしょう。
後ろの方に出てきますが、牛や馬にも効くっておもしろいですね。
本 加持霊薬 奇應丸 一粒六文 十粒入六十文
一 第一 気つけどくけし しよくしやう はらいた
一 むぢ しやく くわくらん 下りはら しぶりはら
一 とんしのものは はらに少しあたたみあれば よみがへるべし 一 気のつきたる又おこりに用いて よし
一 なんざん子の生れかねたる によし 又ゑなの おりぬ によし 血のぼり 気ちがひたる によし
一 きんそう 血どめにはかみくだき付て よし 一 小児きやう風 五かんに妙薬なり
一 ほうそう はしかに用ひ妙薬なり 一 牛馬のなやみにもちひてよし
當山秘方薬師如来
加持霊薬功能異他
三州大濱 寳福寺製
版木 萬金丹
版木の一つをご紹介します。昔「鼻くそ丸めて萬金丹」という言葉遊びがありました。小さく黒い形状で、現在も胃腸薬・整腸剤としてあるようです。
どうやら当時は万病に功能を発揮する妙薬であったもので、寳福寺(林泉寺の末寺)の御本尊 薬師如来さまのお力により、さらに霊薬として、販売されていたようであります。
版木があるところを思うとかなりの人気があって、販売数もかなりあったのでしょうね。
本 加持霊薬 萬金丹 一粒四文 一色四拾文
一 第一 気のつきたる によし
一 づつう めまい 立ぐらみ によし
一 さけのよいざめ によし
一 しょくつかへ はらのいたみ によし
一 ひき風 ねびへ風 によし
一 すべて万病の妙薬なり
當山秘方薬師如来 加持霊薬功能異他
三州大濱 寳福寺製
腕抜き
蓮月のハス
道元禅師御一代掛軸
毎年9月28日 林泉寺においては恒例行事であります。御開山忌法要・秋季檀信徒供養法要が修行されます。その際、曹洞宗の開祖であり、永平寺を開かれたました道元禅師の御一代記の掛軸を本堂に掛けます。この掛軸は箱書きによりますと江戸時代の文政7年(1824)、今から約190年前の掛軸となります。彩色も素晴らしく状態も良好です。現代と比べると、昔の人々は、灯りや道具や情報が限られているような環境でこのような素晴らしい作品が出来たという事は技術力・集中力・根気とすべてが我々より遠く及ばない程、力量のあるの職人さんが多かったと思われます。先人達の努力には頭が下がります。