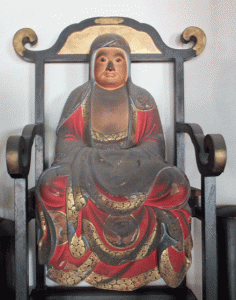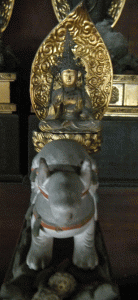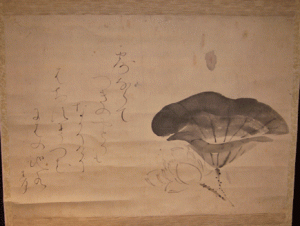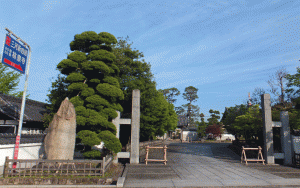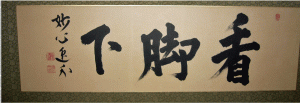達磨大師は遠くインドの地より中国に初めて『禅』を伝えられた方である。本当の弟子が出来るまで、あの拳法で有名な少林寺において9年の長きにわたり、壁に向かって座禅を続けられてみえました。そこで慧可という弟子に出会い、ようやく達磨大師の教えの中心である『禅』を伝える事が出来ました。その異国の顔立ちや座禅の姿勢になぞられて、親しみのある七転び八起きのダルマさんの縁起物になったようであります。そのような方でありましたので逸話も多く、昔から大勢の人々に絵の題材としてモチーフとなりました。雪舟の『慧可断臂図』は国宝でもあり、有名です。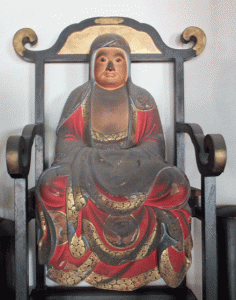
お釈迦さまの大きな特徴である智慧と慈悲、智慧は文殊菩薩さま、そして人々を苦しみから御救い申上げる慈悲はこの普賢菩薩さまが第一です。特徴としては、お釈迦さまの脇侍として、白い象の上で座禅を組む形です。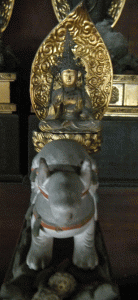
皆さんよく御存じの「三人寄れば文殊の智慧」ということわざの文殊菩薩さまです。この菩薩さまは基本的には単体でお祀りをされる事は少なく、お釈迦さまの脇侍のお1人としてお祀りをされる事が多いです。智慧が第一の仏さまでありますから、片手に巻物を持ち、獅子に乗っているお姿に特徴があります。ちなみに、我々の修行の中心となる座禅堂には、文殊菩薩さまの修行時代のお姿を現している『聖僧(しょうそう)さま』がお祀りされているお寺があります。林泉寺の座禅堂には聖僧さまはおられませんので、お位牌に文殊大士と書いて、安置してあります。
蓮月とは「大田垣蓮月」という。(寛政3年1月8日(1791年2月10日) – 明治8年(1875年)12月10日)は、江戸時代後期の尼僧・歌人・陶芸家。俗名は誠(のぶ)。菩薩尼、陰徳尼とも称した。蓮月は、若き日の富岡鉄斎を侍童として暮らし、鉄斎の人格形成に大きな影響を与えた。
読み 『露ならで つき(月)のやど(宿)りも なかりけり はちすにうづむ には(庭)の池水』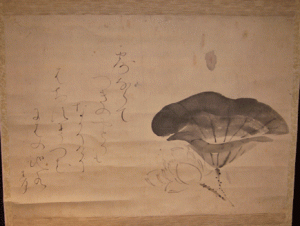
非常に繊細(細く)で力強い(かすれや消えがない)線が特徴です。このような線は私は書けないです。すばらしい。
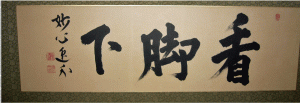
看脚下
「看脚下」脚下を看ろ。禅語では好んで使われる文字である。見るではなくて『看る』を使う。ただぼんやりとではなく、丁寧にしっかりと見つめるということである。日々の我々の生活を見直してみたいものである。
ご本尊さまは聖観世音菩薩坐像、右脇侍は毘沙門天、左脇侍は地蔵菩薩

聖観世音菩薩
寺伝では行基菩薩御作となっていますが、調査が待たれます。
永平寺の秦禅師さまの絵皿であります。『只管』というのは「ただひたすら。一心に実行するという意味です。」